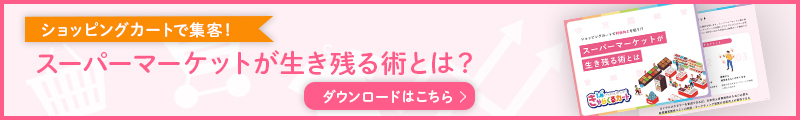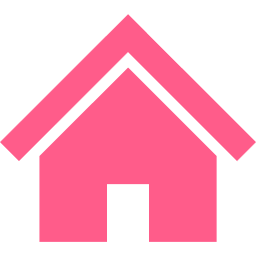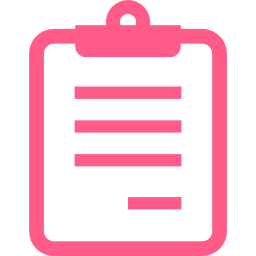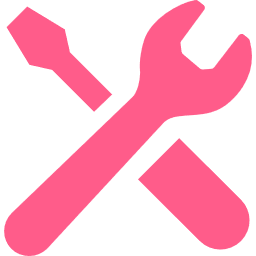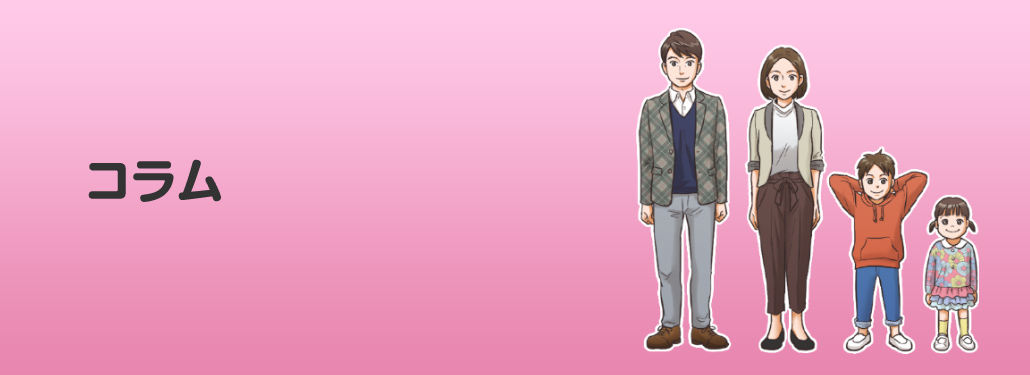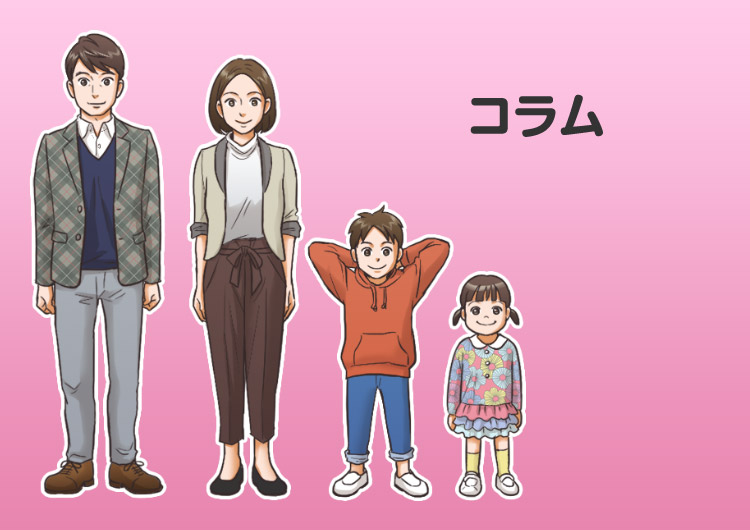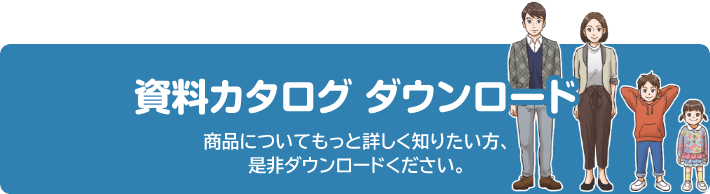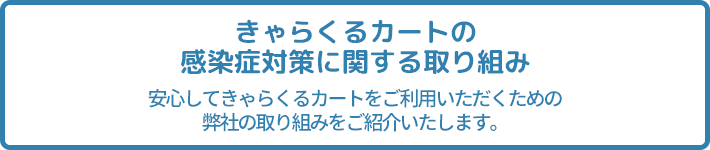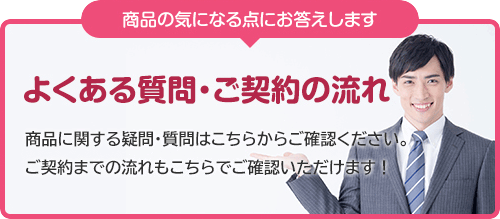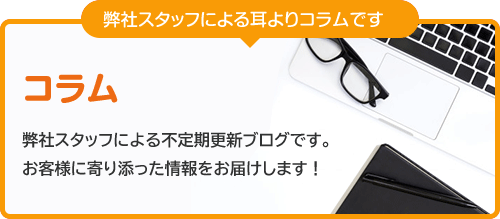SKUは在庫管理の強い味方!基礎知識と活用方法を解説


スーパーマーケットをはじめとした小売店には、在庫管理に関する課題があります。少しでも管理に係る手間を減らし、正確に管理できるよう日々頭を悩ませている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
在庫管理の課題解決のひとつに、SKUの活用があります。本記事では、SKUの意味や考え方・実際に活用するときの考え方をまとめました。

目 次
SKUとは

SKUとは「Stock keeping Unit(ストック・キーピング・ユニット)」の略で、在庫管理上最小の品目数を数える単位です。
日常生活でいうサイズや色などの種類に該当します。SKUはアパレルや小売業など、ひとつの店舗でたくさんの商品を扱う業種でよく使われています。
数字の単位としてSKUを使うこともあります。スーパーマーケットでいうと「4,000SKU、5万ピースの商品」を管理しているという形です。これは「4,000種類・5万点の商品」を指しています。
【関連記事】
スーパーの在庫確認を簡単に!在庫管理システムで業務効率化しよう
なぜSKUが必要なのか
多くの業種で活用されているSKUですが、そもそもなぜ導入されているのでしょうか。これは、SKUの在庫管理にかかる手間を軽減する効果が関係しています。
商品の中には同じものでも色やサイズの違うものがあります。このような商品を混同して管理すれば、特定の色やサイズの欠品・過剰在庫によるバックヤード業務の圧迫を招きかねません。SKUは色やサイズごとにコードをふって管理できるため、商品の混同による問題を予防・改善できます。
ちなみに、SKUと混同されやすい管理単位にJANコードがありますが、SKUとは異なるものです。JANコードは世界共通でルール設定・管理されていますが、SKUは社内独自で自由に設定・管理できます。JANコードよりもより細かく、正確な分類にも対応可能です。
また、JANコードは社外でも活用されますが、SKUは一般的に社内在庫管理の範囲内でのみ使われます。これも両者の大きな違いといえるでしょう。
SKUと混同しやすい用語
SKUには似た用語が複数あるため、混同しないようにそれぞれの用語とその違いをおさえておく必要があります。次はSKUと混同しやすい用語について解説します。
フェイス
フェイスとは店頭に出すSKUを指し、FKU(Face Keeping Unit)の略語で表される場合もあります。
店頭は場所が限られているためすべての商品を並べられるとは限りません。そのため、より正確に在庫管理するには、店頭に出ているものと倉庫内などにあるものを分ける必要があります。フェイスはその区別のために用いられる用語です。
アイテム
アイテムは商品の数を数える時に使われる単語のため、SKUと混同されがちです。
SKUは同じ商品をさらに細かく分けて管理するための単位です。洋服の様に同じサイズ・カラーバリエーションが複数ある場合、アイテムではすべて「1」として数えられますが、SKUの場合は「サイズ×カラーの6SKU」となります。
このように、似ている単語でも指す意味が異なるため、SKUを利用する際は用語ごとの意味や違いを周知しておくことが大切です。
品番または型番
品番は商品管理のための番号で、型番とも呼ばれています。
例えば、期間限定パッケージの場合、元の商品と同一のものとして管理する場合と、別商品として管理する場合があります。この時の区別に用いられるのが、品番です。
同一商品の場合は同じ型番を、別商品として扱う場合は異なる品番をつけて識別します。
ロット
ロットとは一回に製造されるアイテム製造数量のことで、同じ製品のまとまりを指します。製造や輸送効率化を図る際、同じ商品をまとめることがありますが、この時に「製造ロット」「輸送ロット」といった形で使用されます。
一方、SKUは商品の在庫管理上最小単位を数えるための数値です。同じロット内でも、サイズやカラーが異なれば、別の番号を振り分けます。ロットとSKUは管理上必要な単位という点では同じですが、番号の振り方・使用方が異なります。
混同しないよう注意しましょう。
SKU管理するメリット
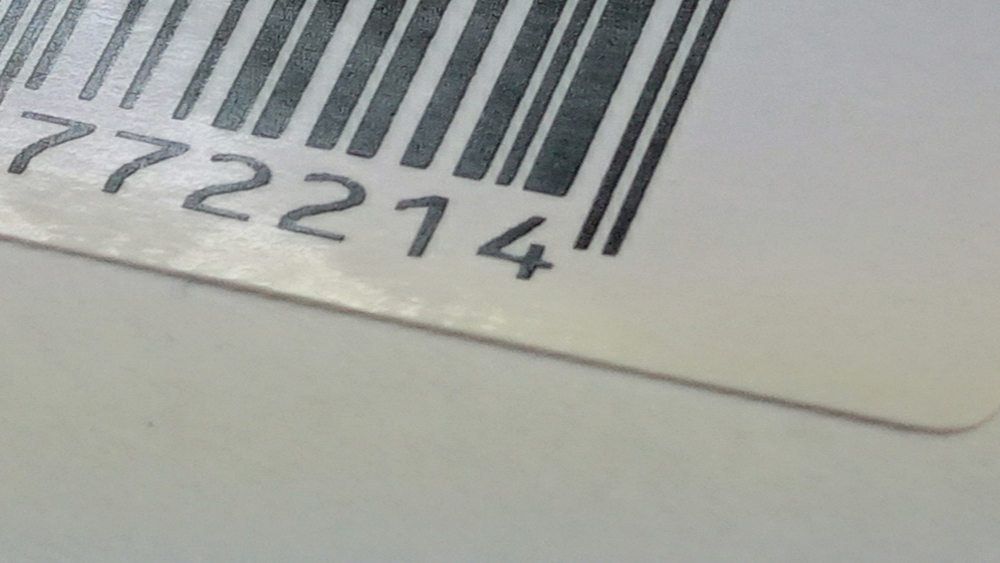
SKUによる管理を導入すると、3つのメリットを得られます。
- 商品在庫管理が簡単にできる
- 発注が簡単になる
- たくさんの商品を管理できるようになる
次はそれぞれの内容について詳しく解説します。
商品在庫管理が簡単にできる
SKUは商品をリアルタイムかつ正確に把握できるため、発注を無駄なく行えます。点数だけでなく色やサイズなどの細かい分類ごとに販売状況を把握することで、在庫管理上のロス削減に役立つでしょう。
また、SKUで発注できるようになれば、発注ミスを防ぐ効果も期待できます。
発注が簡単になる
SKUで発注できるような体制を整えておけば、必要なコードを入力するだけで作業を完了できます。発注作業に必要な時間と手間の削減ができるのも、SKUのメリットです。
JANコードなどを用いた発注の場合、発注の際に色やサイズ・数など、端末を操作して入力しなくてはなりません。SKUならサイズや色ごとに分類されているため、発注作業に入力するのはコードと発注数のみで済ませられます。
発注作業をスピーディーに終えられれば、接客をはじめとした販売活動に注力できます。
たくさんの商品を管理できるようになる
SKUを使えば在庫管理や発注作業のムダ・手間・時間を削減できます。余裕ができた分、商品数を増やすことも可能です。扱う商品数を増やしても、SKUがあれば問題なく管理できます。
SKUが役立つのは、在庫管理だけではありません。店内陳列の際も商品の全体像を把握しながら行えるため、陳列する商品の場所や数もスムーズに決められます。
これらの効果を有効活用できるようになれば、商品数の増加・従来発生していた労力を接客に再配も可能です。結果、売上アップのチャンスをつかみやすくなるでしょう。
SKUのデメリット
SKU導入の際はメリットだけでなく、デメリットも考慮したうえで判断する必要があります。SKUのデメリットもあわせておさえておきましょう。
コストの発生
実際にSKUを導入・運用するには、専用の管理システムやバーコードなどを読み取る専用の機器などが必要です。初期費用がかかるため、小規模店舗などでは導入するとかえってコスト増大につながる恐れがあります。
店舗規模や商品の傾向によっては、SKUを導入するよりも通常管理で把握できる範囲内に商品数をおさえた方が管理しやすい可能性もあります。導入を検討する際は、コストや管理上の手間などを考慮したうえで決定しましょう。
管理方法が難解
SKUのメリットを最大限に利用するには、大量の商品仕分けと陳列作業・商品回転数を向上するための営業活動など、多方面のスキルと経験値が求められます。経験を積めばこれらのデメリットはある程度解消されます。
しかし、管理方法に慣れかつ各スキルが身に付くようになるまでは、デメリットが付きまとうことになるでしょう。
いつか解消されるときが来るとはいえ、業務が難解になるうえに複数のスキルが要求される状況に陥るのは、無視できないデメリットといえます。
SKUの考え方

便利なSKUですが、有効活用するには基本の考え方をおさえておく必要があります。SKUを考えるときのルールもおさえておきましょう。
SKUの設定は、バーコード、つまりJANコードを基準に考えます。JANコードは国際的なルールで振られており、別商品扱いのものは、パッケージが似ていても異なるコードがふられています。SKUは自社ルールでコード振り分けができるため、混同しないように注意しながら設定しましょう。
また、SKUを設定する際は、分けた方がよい場合と一概にはそうは言えない場合があります。それぞれのケースについて解説するので、ふり分けの参考にしてください。
SKUを分けた方がいい場合
SKUを設定する際に分けた方がよい例として、3つのケースがあります。
- 内容量だけ違う
- 料金だけ違う
- 単品販売していたものをセット販売する
どれも顧客が間違って商品を購入する恐れのあるケースです。返品やクレームにつながる恐れがあるため、これらの商品は分けて登録しましょう。
特に料金は売上をはじめとした指標にも大きく影響が出るため、必ず違うコードを付けてください。
同じ商品でも異なる価格のものを同一に扱えば、イベント施策の効果測定にも影響します。SKUが商品・料金ごとに別れていればできた分析も、混同した状態では不可能です。
商品・施策分析を正確に行うためにも、SKUの割りふりには注意しましょう。
一概にSKUを決められない場合
同じ商品でも異なる要素があれば分けた方がよいSKUですが、一概には決められない場合もあります。同じSKUなのに、デザインが異なる場合です。
デザインやパッケージが異なるだけで価格などは同じ場合、一概に別管理すればいいとはいえません。
在庫が豊富にある商品や、コラボデザイン・パッケージ目当ての顧客がいるものは、分けて管理した方がクレームや過剰在庫によるトラブルを防止できます。
一方、在庫が少なく、出荷が速い商品は分けて管理するとかえって不便になる恐れがあります。
倉庫の出荷担当者は、少ない商品から出荷するのが一般的です。こうした商品は分けなくてもすぐに店舗に来て店頭に並べられる関係から、売れるスピードも他商品に比べると早い傾向にあります。
店舗で管理する時間も短いため、分けなくても問題ありません。SKUは、細かくコードを割りふればいいわけではないことも覚えておきましょう。
SKUを導入している業界の考え方
次は、SKUを導入・運用している業界を活用事例として紹介します。導入や運用のヒントとしてご活用ください。
アパレル業界の場合
アパレル業界の場合、同じ商品でもブランド・サイズ・カラーなどによって商品を明確に区別しなくてはなりません。例えば、以下の商品があったとします。
- ブランドコード:110
- カラーコード:BLU
- サイズコード:M
この商品をSKUで管理する場合、上記の内容を指す「110-BLU-M」といったコードが振り分けられます。
文具店の場合
アパレルと同じように同一商品でもそれぞれ区別する必要があるのが、文具店やそこで取り扱う商品です。例えば黒の油性ペンなら、メーカー・ペンのタイプ・インクカラーで以下のように区別します。
- ブランドコード:110
- ペンコード:OILPEN
- カラーコード:BLK
これをSKUで管理する場合、「110-OILPEN-BLK」となります。
SKU設定における注意点

SKUを設定する際注意すべき点は、考え方だけではありません。以下の注意点も念頭に置きながら作業しましょう。SKUコード設定における注意点を解説します。
重複は避ける
SKUを設定するうえで絶対にやってはならないのが、コードの重複です。同じコードを設定してしまうと、異なる商品が同じコード内に交じってしまいます。これではSKUを設定した意味がありません。
コードの重複に気が付かないまま顧客に商品を販売してしまうと、商品間違いによるクレームが発生する恐れがあります。また、本来必要ない商品を大量に発注して在庫を圧迫する事態が発生する可能性もあります。
このような事態を避けるためにも、商品は基本増え続けることを念頭に置きつつ設定してください。重複対策としては、コードを連番で付けるなどの対策が有効です。
桁数をそろえる
SKUの機能を活かすためにも、コードの桁数はそろえて付けましょう。桁数をそろえておくと、Excelやシステム上で管理しやすくなります。
なお、コードが短すぎると新しい商品を設定する際手間がかかります。長すぎるとシステムが認識しにくくなるため、どちらの場合も不便です。設定する際は管理しやすい長さで設定しましょう。
ちなみに、SKUは一般的にJANコードに合わせて13桁で管理されています。管理上問題がなければ、13桁コードでの管理がおすすめです。
大文字・小文字は統一する
桁数だけでなく、コードに使う文字も統一しましょう。大文字と小文字が混同していると、出荷や発注の際に間違える恐れがあります。
また、大文字と小文字を変えただけで登録すると、システムが同じコードとして判断する恐れがあります。紛らわしい表現は入力や認識のミスの元です。特によく似た商品を登録する際はご注意ください。
先頭にはゼロを置かない
SKUの先頭にゼロを付けると、商品管理システムに認知されません。たとえば、異なる商品に以下のようなコードを割りふったとします。
- 01234-ZAIKO-AK
- 1234-ZAIKO-AK
この場合、ゼロが認識されないため、同じコードだと認識され、片方が無効になる可能性があります。入力ミスにもつながるため、先頭にはゼロ以外の英数字を使いましょう。
SKU管理で効率よく商品を管理しよう
SKUを導入すれば、商品管理や発注作業をより正確に、効率的にできるようになります。うまく言活用すれば、売上アップの機械を掴むのにも役立つでしょう。在庫管理や発注に関する課題を抱えているなら、導入をおすすめします。